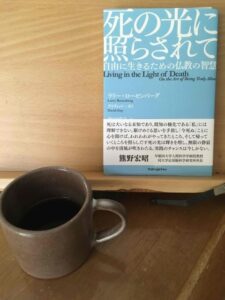変わる葬儀:生成AIで故人を再現
事務局長の佐藤です。
8月21日付の読売新聞の夕刊に「故人を生成AIで再現」という記事がありました。これは亡くなった人をAI(人工知能)で再現し、葬式などでスピーチをしてもらうというものです。
記事ではまず、98歳で亡くなった人が、葬儀の終盤に自分の葬儀への会葬のお礼を述べる例が紹介されていました。これは生前、葬儀とは関係なく故人が趣味について語ったビデオをもとに制作した生成AIが喋ったもの。動画を制作した葬儀会社では、サービスに先立ち倫理委員会を設置してガイドラインを話し合ったそうです。その中で、AIの個人と対話をする「対話型」は、故人が望まない内容を発話させられる可能性があるために実行しなかったそうです。また別の会社でも、例えば亡き父が結婚式で祝辞を述べるなど好評を博しているといいますが、相談したグリーフケア専門家から「依存の可能性が高い」として「対話型」は回避したそうです。
一方では積極的に対話型のサービスを始める会社も紹介されています。ただ、この会社では悪用を防ぐため、受注の際には商用への二次利用を禁じるなどの措置を取っているとのことです。
この流れがどこまで広まるかは未知数ですが、私としては若干批判的です。
いくらAIといっても本人でないことは確かです。本人が「言いそうなこと」と「言うこと」は全く違うと思います。ただ、それによって遺族が慰められるのであればそれはよしとしなければならないと思いますが。
さらに記事にもあった対話型は問題をはらんでいます。
例えば、夫を亡くした妻が、仏壇の前で亡き夫に話しかける場面を想像します。今までであれば、当然ですがいくら話しかけても反応はないので、最後には「そうよね、あなた」と独り言を言いながら自分で納得するでしょう。この「独り言」の行為が、遺族の癒しになると思います。もし仏壇の前で亡き夫のAIと対話をしたとしたら、ある人はAIの夫に依存するかもしれませんし、またある人はAIの夫とケンカを始めるかもしれません。すると供養どころではなくなります。
・・・みなさんはどう思うでしょうか。
<記事出典>
・故人を生成AIで再現、葬式であいさつ・対話型サービス…依存や死者の尊厳傷つけるリスクも(読売新聞オンライン2025年8月21日)
佐藤 厚
(感謝! アイキャッチ:daily shortzによるPixabayからの画像)