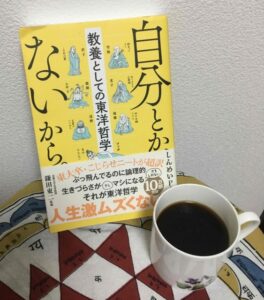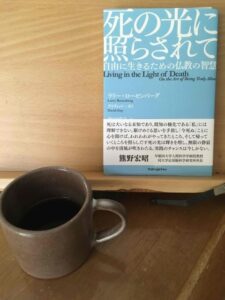これってあり? 地蔵菩薩像霊験記にびっくり
事務局長の佐藤です。
以前、仏教会の漢文読書会で常謹撰『地蔵菩薩像霊験記』を講読していました。これは中国宋代に成立したもので、地蔵菩薩の霊験譚を32種あつめたものです。この中でびっくりした話があったので紹介します。現代語訳を出します。
----------------------------------------------------
唐簡州鄧侍郎家杖頭地藏感應記第十
簡州金水県(現在の四川省)に鄧氏という侍郎(今の日本では事務次官)がいました。
ある日、隣の家の道の横に、折れた杖があるのを見ました。その杖の頭には僧侶の形が彫られていましたが、何の像かはわかりませんでした。
侍郎はもともと仏を信じていたので持ち帰って壁に挿し、礼敬して立ち去りると、やがてそのことは忘れてしまいました。二三年の後、侍郎は急に病気にかかって死んでしまいました。ただ、胸のあたりが暖かかったので(家族は)彼を葬ることをしませんでした。
すると一日一夜ののちに蘇りました。侍郎は涙を流しながら冥途の因縁を話しました。
(侍郎の話)
死ぬとすぐに二騎の冥途の使者がやってきて、私を連れて大きな城門に着きました。馬から降りると私を連行して城に入り、(閻魔)王の役所の前に着いたのです。その庭には百千万人もの繋がれた人々がいました。
王が怒って私を叱りつけようとしたその瞬間!姿が醜い一人の沙門が王の役所の前にやってきました。王は、遠くからこれを恭しく迎え、席から起き上がり、合掌して次のように言いました。
王 「沙門大聖よ、どうして突然いらしたのですか」。
沙門 「あなたが誡めようとしている侍郎は私の檀越である。その恩を返したいので、一つ放免してやってくれまいか。」
王 「(侍郎の)業は既に決定しています。命も食も尽きました。放免するのは難しいです。」
沙門 「私は昔、三十三天の善法堂で、仏の付属を受け、業が定まった人を救ってやったことがある。諸々の悪人がいるというのは今日に始まったことではない。まして侍郎は重い犯罪でもない。どうして助けてやれないことがあろうか」。
王 「大士は大きな願いが堅固で、それは金剛山のように動きません。ですから人間世界に返しましょう。食が尽きていますが小豆を授けましょう」と。
沙門は喜び、侍郎の手を引いて生への道に入り、別れを告げました。その時、侍郎は沙門に少し待ってくださいと言い尋ねた。
侍郎 「私を助けてくださったあなたはどなたですか?」
沙門 「あなたは知りませんか・・・・私は地蔵菩薩です。あなたがこの世にいた時に、道の脇で私の姿を見て、事情もわからないが壁の中に挿してくれました。あれは子供が戯れに杖の頭に刻んで像としただけです。それはただ首だけがあって、そのほかの部分はありません。それゆえ形が醜いのです」と。言葉が終わると、急にいなくなりました。
(侍郎の話おわり)
----------------------------------------------------
病で死んだ侍郎が、あの世での裁きを受ける直前、生前に助けた地蔵菩薩に救われ、生き返るという話です。
「自業自得」、自分がなした行為の結果=業は自分にふりかかる、というのは仏教の鉄則だったはずです。それを地蔵菩薩が、自分の檀家だったから、放免してはくれまいか、というのは何かムシのよい話に聞こえます。この王とは閻魔王と思いますが、「業は既に決定しています。命も食も尽きました。放免するのは難しいです。」という原則を主張するのが何か哀れに思います。
ただ、穿った見方をすれば、地蔵菩薩を助けた行為も実は業の中に入っており、それによって助けられた。ゆえに「自業自得」の教説を破壊するものではない、とも考えられますが、うーん、いかがでしょうか。
佐藤厚
(感謝! アイキャッチ画像:chian88によるPixabayからの画像)