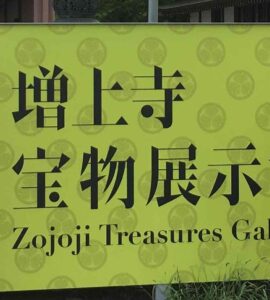お盆にお墓を考える(1)
こんにちは。事務局長の佐藤です。
今回はお盆シーズンということでお墓について書いてみます。
昨今のお墓をめぐる話題の一つが「墓じまい」。その背景には、少子化などのために、家を中心とした代々の墓地を守ることができなくなったことがあります。
ところで今後増えると思われるのは、子どもがいない2人だけの夫婦の場合です。どちらかが先に亡くなれば、残った方が葬式をやることになりますが、問題は残った方の葬式やお墓の問題です。
これに関連して私が注目しているのが、事前に登録しておくと遺体の引き取りから葬祭、霊園管理までしてくれるNPO法人です。
ここの特徴は、将来同じ墓に眠る予定の人々を「墓友(はかとも)」と呼び、定期的に交流イベントを行うことで、これがあれば亡くなった後も周囲が「見ず知らず」の人ではなくなります。
設立者でもあり理事長は、家族や墓について研究してきた社会学者です。また、この法人は宗教と無縁なわけではなく法要には僧侶が参加しています。つまり、従来は、<寺院ー墓ー家>のように、寺院と家が葬儀・法要や墓を媒介として、世代を超えてつながりを持っていましたが、いま紹介した例では、<墓地運営団体(+僧侶)ー墓-個人>のように、家の存続が難しいため、墓地運営団体が個人と関係をもち、そこに僧侶が関連するようになっています。社会が変わると宗教のあり方も変わっていく一つの例と思います。
<参考>
NPO法人エンディングセンター